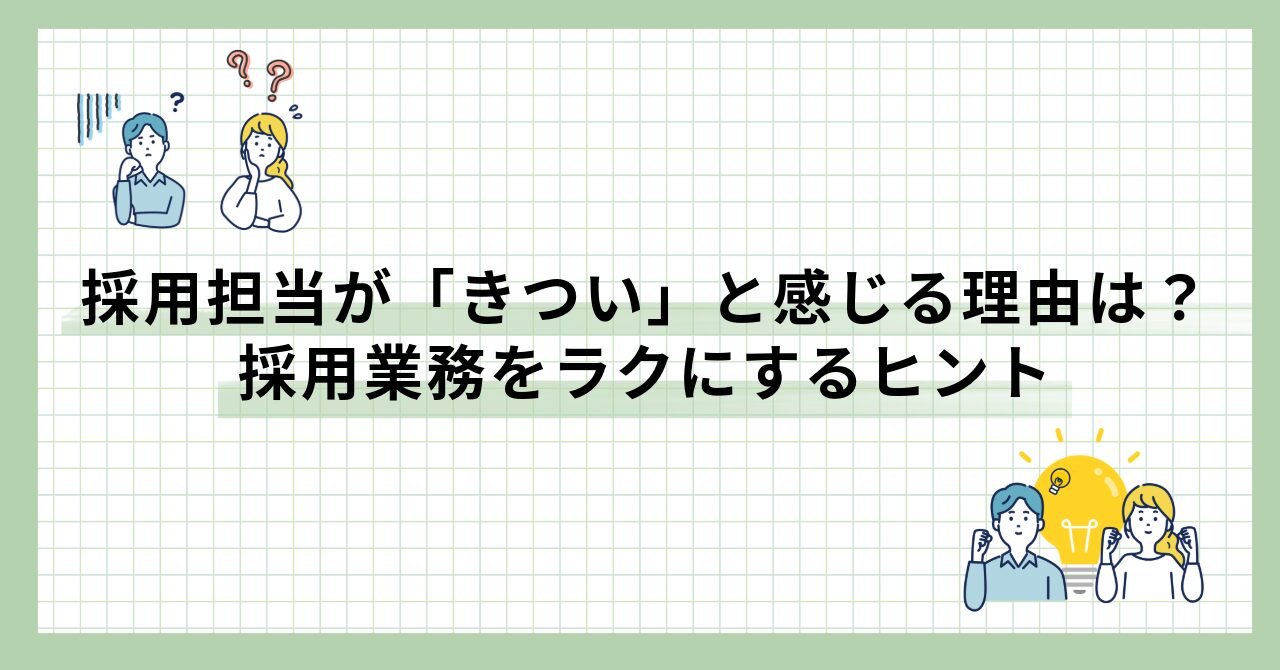「採用担当の仕事がきついのはなぜ?」と悩んでいませんか?本記事では、応募が集まらない理由や現場との板挟みの負担などの根本原因から、改善のための具体策、業務を軽くする支援サービスまでわかりやすく解説します。
採用担当が「きつい」と感じやすいシーン
採用担当者の仕事は、想像以上に多岐にわたります。求人票を出して応募を待つだけでなく、社内調整、面接設定、応募者対応、データ管理、採用広報など、日々の業務は細分化され、しかも同時進行で進めなければなりません。表面上は「人を採る」というシンプルな目的のように見えても、実際には企業の印象や応募者体験を左右する責任の重い仕事です。
採用が立て込む時期は休みが取りづらくなる
採用活動には繁忙期があり、そのタイミングが来ると、日常の働き方は一気に変わります。応募者対応や面接調整が次々と入ってくるため、スケジュールは常に埋まり、気づけば昼休みも削って対応していることが珍しくありません。本来であれば落ち着いて取り組みたい選考書類の確認も後回しになり、残業続きの状態が続くと、心身が休まる時間がどんどん減っていきます。
結果として「この時期は本当に休めない」という焦りや疲れが蓄積され、採用担当の仕事がきついと感じる大きな要因になります。
募集をかけても応募が集まらない
応募が来ない状況は、採用担当にとって精神的な負担が特に大きい場面です。求人票を改善し、媒体を増やし、社内にも協力を依頼しているにもかかわらず応募が届かないと、「自分のやり方が悪いのでは」と責任を感じてしまうこともあります。
さらに、現場からは「まだ応募来ないの?」と何度も聞かれ、そのたびに対応に追われることでプレッシャーが積み重なります。応募が集まらない原因は市場環境や労働条件、競合状況など多岐にわたるにもかかわらず、自分一人で改善しなければならないように感じてしまう点が、採用担当がきついと感じる理由につながります。
社内外の板挟みでストレスが大きくなる
採用担当が強いストレスを感じやすい場面の一つが、社内と求職者の間で板挟みになる瞬間です。現場からは「早く人を採用してほしい」「もっと理想に近い人を連れてきてほしい」といった要望が寄せられる一方、求職者からは「できるだけ早く選考結果を知りたい」「条件面を詳しく教えてほしい」といった別の期待がかかります。双方の希望が一致しないことは珍しくなく、その調整役を担う採用担当には、常に慎重で丁寧なコミュニケーションが求められます。
しかし、それぞれの立場の思いや事情を理解し、最適な落としどころを探る作業は決して簡単ではありません。現場へは市場状況の厳しさを説明しながら採用条件の見直しを提案し、求職者には社内での調整状況を伝えながら納得感を得てもらう必要があります。このように両側からのプレッシャーを受け続けることで、「誰の期待も裏切りたくない」という気持ちが重荷となり、精神的な疲労が蓄積していきます。
採用担当が特に「きつい」と感じるタイミング
採用担当の仕事は、一年を通して常に一定の業務があるわけではありません。時期によって業務量が大きく変動し、特定のタイミングになると、普段よりも圧倒的に負荷が高まります。計画通りに動かしたい気持ちがあっても、社内の状況や市場環境によってスケジュールが大きく左右されることも珍しくありません。
ここでは、採用担当が「特にきつい」と感じやすい3つの代表的な時期を見ていきましょう。
新卒採用の広報スタート〜内定出しの時期
新卒採用は年間スケジュールが決まっているため、「いつから忙しくなるか」が明確です。しかし、わかっていても準備の幅が広く、想像以上の負担がかかります。広報開始時期には説明会の企画や資料作成、イベント出展などやることが一気に増え、そのうえ応募者が増え始めると、面接調整・書類選考・学生対応が同時進行で押し寄せてきます。
さらに内定出しの時期が近づくと、複数の候補者との日程調整や辞退防止のフォローなど、心理的にも気を抜けない場面が続きます。これらの業務が期間限定で集中するため、新卒採用の時期は、採用担当にとって一年で最も緊張感の高いシーズンといえるでしょう。
中途採用のニーズが一気に増える時期
中途採用は新卒とは異なり、突発的にニーズが高まるのが特徴です。予想していなかった欠員が出たり、新規プロジェクトの立ち上げで急に人材が必要になったりすると、短期間で実務に対応できる人材を確保しなければなりません。
このような“急ぎの採用”が発生すると、求人票の見直し、媒体選定、スカウト送信、面接日程調整など、通常よりもスピードが求められます。現場からは「早く人を入れてほしい」という期待が一気に高まり、採用担当としてはプレッシャーのかかる時期になります。とくに複数部門から同時に依頼がくる場合は業務の優先順位付けも難しく、精神的な負荷も高まりがちです。
採用担当の人数が減り、業務が集中する時期
人事部門では、異動や退職、長期休暇などによって採用担当の人数が減る場面があります。こうした状況が重なると、本来2〜3人で回す業務を一人でカバーしなければならないケースも出てきます。
応募者対応も面接調整も現場とのコミュニケーションも、すべてのタスクが採用担当一人に集中すると、業務が次々と積み上がり、手が回らなくなってしまいます。仕事の質を落としたくない一方で、時間は限られているため、どこで線を引くべきかの判断にも迷いが生じます。こうした“人的リソース不足”は、採用担当が強くストレスを感じやすい典型的なタイミングです。
採用業務が「きつい」と感じる根本原因
採用担当の仕事がつらく感じる背景には、単に業務量が多いという表面的な問題だけではなく、“構造的な原因”が潜んでいることがよくあります。同じ作業でも、人や会社によって負担の感じ方が異なるのは、この根本的な要因が整理されていないことが影響しているからです。
まずは、採用業務がなぜ重くのしかかるのか、その核心を見ていきましょう。
採用フローが整理されておらずムダが多い
採用がきつく感じる大きな理由のひとつが、「業務フローの複雑さ」です。本来であれば、応募受付から内定までの流れは明確であるべきですが、実際には部署ごとにやり方が違ったり、以前の担当者のやり方がそのまま引き継がれていたりと、整理されていないケースが少なくありません。
その結果、同じ作業を何度も繰り返したり、誰かの確認待ちで業務が滞ったりして、本来必要のない作業に時間を取られてしまいます。こうした“ムダな動き”が積み重なるほど、採用担当者の仕事はどんどん重たくなり、追われるような感覚が強まっていきます。
求める人物像が曖昧で採用の軸が定まらない
「どんな人を採用したいのか」がはっきりしていないと、採用活動全体が迷走します。現場の希望が曖昧だったり、複数の担当者の意見がバラバラだったりすると、求人票の内容も評価基準もぼやけてしまい、選考のたびに判断基準が変わってしまいます。
その結果、応募者とのミスマッチが増え、面接を重ねても採用につながらない状況が続くことになります。採用担当としては「そもそも何を基準に判断すればいいのか」がわからなくなり、毎回の調整や伝達に余計な時間とストレスがかかるようになります。軸が定まらない状態で採用活動を続けるのは、精神的にも実務的にも非常に負担が大きいのです。
自社の強みが言語化できず、魅力を伝えきれない
採用市場が売り手優位となっている現在、求職者は数ある企業の中から“入社する価値のある会社”を選んでいます。そのため自社の魅力を適切に伝えることが欠かせませんが、実際には「強みが明確になっていない」「どんな会社なのかが言語化できていない」という企業も多く存在します。
強みが言語化できていないと、求人票も面接での説明も曖昧になり、求職者の興味を引くことが難しくなります。採用担当者としては「魅力を感じてもらえないのは説明が悪いのでは」と不安になり、プレッシャーが大きくなってしまいます。これは、応募が集まりにくい状況とも直結し、採用の負担をさらに重くする要因となります。
そもそも採用担当に合わない
採用担当の仕事には、コミュニケーション力や調整力、スピード感など、いくつかの必須スキルがあります。しかし、すべての人がこれらの能力を自然に発揮できるわけではありません。たとえば、人と話すのが苦手な人が面接やクロージング対応を担当すると、それだけで大きなストレスにつながります。
また、マルチタスクが苦手な人にとって、常に複数の案件を同時並行で処理しなければならない環境は負担が大きいものです。「向いていない」と感じながら仕事を続けていると、ちょっとした出来事でも大きなダメージになり、採用業務全体が過剰にきつく感じられてしまいます。これは個人の努力不足ではなく、業務と適性のミスマッチが引き起こす問題です。
採用担当に求められるスキル
採用担当の仕事は、単に応募者と面接をするだけの業務ではありません。候補者の見極め、現場の要望調整、採用市場の把握、会社の魅力づくりまで、多岐にわたる役割を担っています。
そのため、成果を出す採用担当者は、共通していくつかのスキルを身につけています。これらのスキルは才能ではなく、業務を通じて磨かれていくものなので、今「きつい」と感じている人にとっても、今後の改善のヒントになります。
コミュニケーション能力
採用担当にとって、コミュニケーション能力はもっとも重要なスキルのひとつです。候補者とのやり取りでは、応募の背景や希望条件を丁寧に引き出しながら、企業の魅力を適切に伝える必要があります。一方で社内では、現場責任者やマネージャーと採用要件を擦り合わせ、選考フローや判断基準を共有する役割も担っています。
内外の関係者とスムーズにコミュニケーションを取れると、選考速度が上がるだけでなく、ミスマッチも減りやすくなります。反対に、情報の伝達が不十分だったり、意図が正しく伝わらなかったりすると、それが採用遅延や誤解につながり、結果的に採用担当者の負担を大きくしてしまいます。
傾聴力
候補者の本音を引き出すためには、話す力以上に「聴く力」が求められます。応募者は面接の場では緊張しやすく、自分の考えをうまく言語化できないことがあります。そこで採用担当が適切に質問し、相手の言葉を受け止めながら整理していくことで、候補者の価値観や働き方、将来像が見えてきます。
また、現場担当者の不安や希望を正しく理解することも、傾聴力の重要な役割です。聞いた内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、背景にある課題や本質的なニーズを読み取ることで、よりよい採用計画を提案できるようになります。
営業力
「営業力」という言葉は採用業務と無関係に聞こえるかもしれませんが、実は非常に大切なスキルです。候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらうためには、企業の魅力や働く価値をわかりやすく伝える必要があります。仕事内容だけでなく、会社の雰囲気や将来のビジョンなどを丁寧に説明し、魅力づけを行うのは採用担当の役目です。
特に中途採用では、複数企業から声がかかっている候補者が多いため、どれだけ自社の強みを伝えられるかが内定承諾率に大きく影響します。営業のように「価値を伝え、相手の判断を後押しする力」は、採用成功に直結する重要な要素といえます。
情報収集力
採用活動を成功させるためには、市場の動向を正しく把握する力が欠かせません。たとえば、「今どの職種の採用が難しいのか」「競合企業はどんな求人条件を提示しているのか」「求職者が重視しているポイントはどこか」といった情報は、採用戦略の質を大きく左右します。
こうした情報を適切に集められると、求人票の改善や採用チャネルの選定、面接での訴求ポイントの検討など、具体的な施策に落とし込みやすくなります。逆に情報不足のまま採用活動を進めると、努力の方向性がずれてしまい、余計な負担が増えてしまいます。
調整力
採用担当の仕事は、社内外のあらゆる関係者をつないで進める業務です。そのため、日程調整や書類確認、選考基準のすり合わせなど、細かい調整が常に発生します。これを正確かつ効率的に行う力が調整力です。
調整がうまくいかないと、連絡齟齬や選考遅延が起き、候補者の離脱にもつながりかねません。
採用担当者の辛さを軽減するための具体的な施策
採用担当者の「きつさ」は、単なる忙しさではなく、仕組みや体制の問題が複雑に絡み合った結果です。だからこそ、根性や努力ではなく、業務設計と環境づくりの見直しが必要になります。
この章では、日々の業務を少しでもラクにし、採用活動をスムーズに進めるための具体的な方法を紹介します。
業務の整理から社内連携、ツール活用まで、現場ですぐ実践できる改善策を見ていきましょう。
採用プロセスの見直しと業務簡略化
採用担当者の業務を軽くする第一歩は、採用プロセスの棚卸しです。
日常の業務をすべて書き出してみると、重複やムダな手作業が想像以上に多いことに気づくはずです。たとえば、求人媒体ごとに異なる管理シートを使っていたり、メールでのやり取りが煩雑になっていたりするケースです。
これらを整理し、同じ情報を複数回入力する作業は自動化ツールに置き換えるだけでも効率は大きく変わります。
また、選考基準や評価方法を統一しておくことで、面接官ごとの判断のばらつきが減り、再調整の手間も少なくなります。採用のスピードと質を両立するには、プロセスを「属人的な作業」から「再現性のある仕組み」へ変えていくことが重要です。
社内連携強化と現場社員の巻き込み
現場社員が採用活動に関わることで、求める人物像の精度が上がり、採用後のミスマッチも減少します。
具体的には、募集要件を決める段階から現場の声を取り入れ、面接にも一部参加してもらうのが理想です。
また、採用進捗や応募状況を社内で定期的に共有し、現場にも“採用はチームの仕事”という意識を持ってもらうことが大切です。
採用活動は、組織全体で取り組む「共創プロジェクト」です。現場を巻き込み、協力体制を整えることで、担当者一人のプレッシャーを大きく減らすことができます。
早期離職防止のための入社後フォロー体制構築
採用の成功とは、内定者を出すことではなく、入社した人が活躍し続けることです。
まずは、入社初日のオンボーディングを丁寧に行い、社内文化や仕事の流れをスムーズに理解できる環境を整えましょう。
さらに、入社後1か月・3か月といった節目でフォロー面談を実施し、不安やギャップを早めに解消することが大切です。メンター制度を導入すれば、直属の上司とは別の相談相手を確保でき、安心して職場に馴染めます。
このようなフォロー体制をつくることで、離職率が下がるだけでなく、採用担当者自身が「採用して終わりではない」とやりがいを感じられるようになります。
採用アウトソーシングや管理システムの活用
限られた時間と人手で成果を出すには、外部リソースやツールの活用が欠かせません。
たとえば、採用アウトソーシングを利用すれば、スカウト配信や候補者との連絡調整などの定型業務を専門スタッフに任せることができるため、担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。
また、採用管理システムを導入すれば、応募者データや選考進捗を一元管理でき、ミスや抜け漏れが激減します。SlackやGoogleカレンダーと連携できるツールも多く、社内の情報共有もスムーズです。
“人の頑張りで支える採用”から“仕組みで回す採用”へ。この意識の転換こそ、採用担当者の負担を根本から軽くする第一歩です。
採用課題を解決するための支援サービス3選
採用業務を効率化するためのツールやサービスは数多くありますが、重要なのは自社の課題に合ったものを選ぶことです。ここでは、採用担当者の負担を軽減し、限られた時間と人員でも成果を上げやすい代表的な3つのサービスを紹介します。
HERP Hire
HERP Hireは、人事だけでなく現場社員も巻き込み、チーム全体で採用を進められる採用管理システムです。候補者の基本情報や評価、社内メンバーのコメントまで、すべてを一画面で確認でき、情報共有の手間を大幅に削減することができます。
また、Slackと連携できるため、面接調整や選考コメントの共有もスムーズです。面接官はシステムにログインせずに通知や確認ができるなど、現場の負担を最小限に抑えた設計が特徴です。
採用担当者の孤立を防ぎ、“チームで成果を出す採用体制”を築くことができるツールです。
ジョブカン採用管理
ジョブカン採用管理は、応募獲得から採用決定までの業務を一元管理できるクラウド型採用管理システムです。求人情報や画像を入力するだけで自社の採用サイトを簡単に作成でき、IndeedやGoogleしごと検索にも自動連携します。
また、採用サイトや求人媒体、エージェントなどさまざまな経路からの候補者情報をまとめて管理し、選考状況や評価までを可視化し、一元管理できます。
シンプルで直感的な操作性と、初期費用が不要な手軽さが多くの企業に選ばれている理由です。
FREE JOB
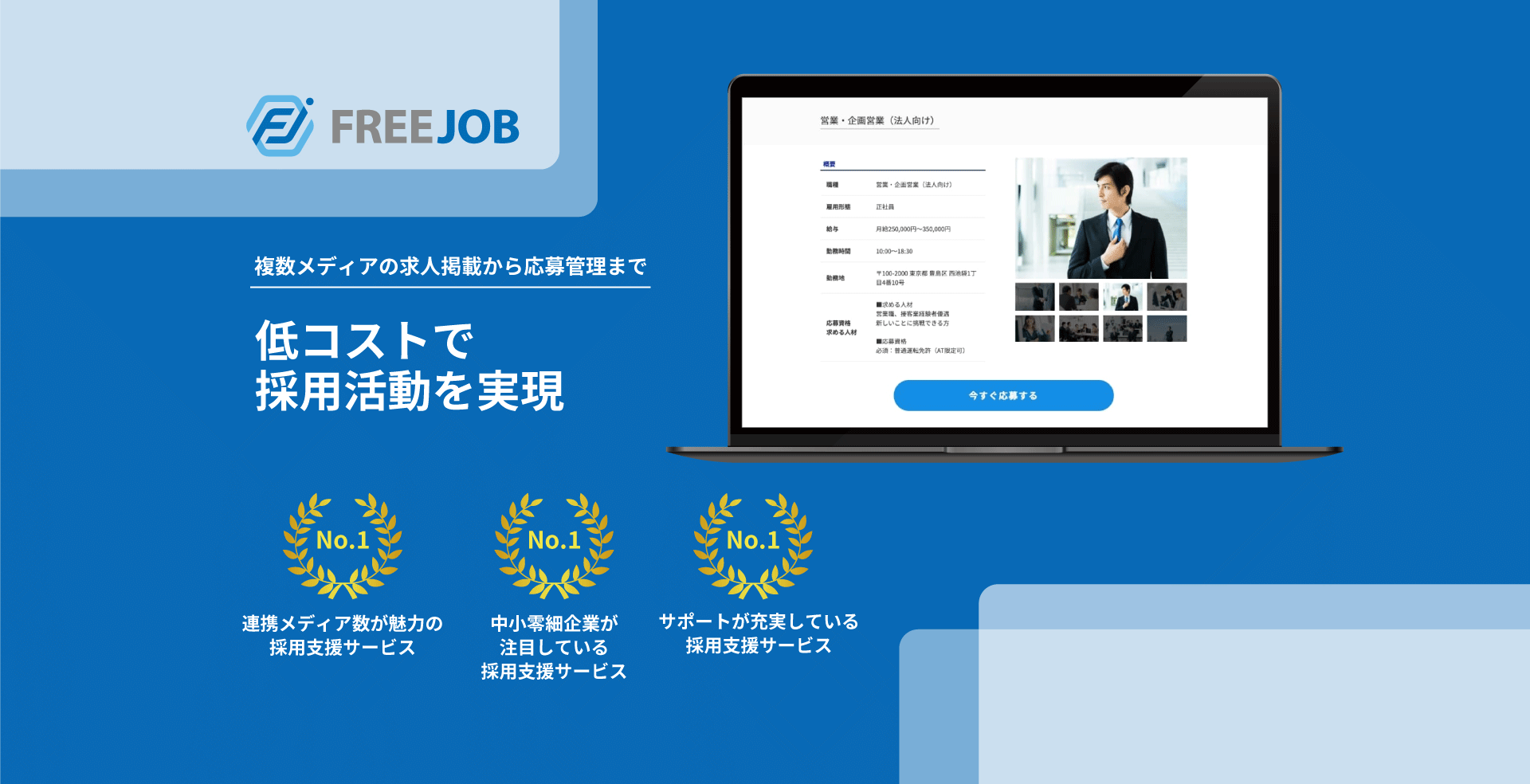
FREE JOBは、採用ページの作成から求人メディアへの掲載、原稿のブラッシュアップまでをワンストップで支援する採用支援サービスです。専任担当者を置く余裕がない企業でも、短期間で成果を上げやすい設計になっています。
スタンバイや求人ボックス、Google for Jobsなど複数の採用メディアへの掲載を代行し、媒体ごとの管理や更新の手間を削減。さらに、採用コンシェルジュが求人内容の改善や写真差し替えなどをサポートし、応募数アップにつなげます。
単なる掲載サービスにとどまらず、採用活動を伴走支援する“頼れるパートナー”として多くの企業に選ばれています。
\採用支援サービス「FREE JOB」のご相談はこちら/
採用担当として働く“やりがい”とは?
採用担当の仕事は、確かに負荷が高く、日々の業務に追われていると「この仕事は大変なことばかりだ」と感じてしまうことも少なくありません。しかし一方で、採用ならではの“大きなやりがい”があるのも事実です。選考に関わる一つひとつのプロセスは、組織の未来をつくる基盤であり、自分の働きかけが会社全体に影響を与える瞬間に立ち会えます。
この章では、採用担当だからこそ感じられる3つのやりがいを紹介します。
採用した人材が活躍し組織に貢献してくれる
採用担当として最も大きな喜びを感じるのは、自分が採用に関わった人材が入社後に実際に活躍し、組織に良い影響を与えてくれる瞬間です。面接での印象や価値観、強みを見極めながら「この人ならきっと成長できるはず」と期待して送り出した人が、現場で成果を上げている姿を見ると、選考の判断が間違っていなかったという確かな手応えにつながります。
とくに新卒採用などで、学生だった候補者が社会人として成長し、リーダーとして活躍する姿を見られるのは、採用担当ならではの醍醐味です。「人の人生の大切な転機に関わる」という責任は大きいですが、その分だけ成果を目の当たりにしたときの達成感は非常に大きなものになります。
会社の体制づくりに携われる
採用は単なる“人を集める仕事”ではなく、会社の未来を形づくる重要な役割です。どんな人がどのタイミングで入社するかによって、組織の雰囲気やチームの強みは大きく変わります。つまり採用担当は、企業の成長に直接関わる“組織づくりの中心”といえる存在です。
また、採用方針や選考基準を整える過程で、現場の課題や経営陣の意向に触れる機会も多く、会社全体の動きを知ることができます。こうした経験は、人事という枠を超えて事業や組織運営への理解を深めることにつながり、自分自身の視野が大きく広がります。
採用スキルが自身の成長につながる
採用活動を通じて身につくスキルは、どれも汎用性が高く、キャリアに直結します。たとえば、候補者の話を引き出すヒアリング力、現場との関係性を築くコミュニケーション力、状況に応じて優先順位を判断するマルチタスク力など、人事以外の職種でも活かせる能力が自然と磨かれていきます。
さらに、経営視点で組織の課題を捉える力や、採用市場を読み取る情報感度も身につき、人事としてのキャリア幅を広げることができます。採用担当としての経験は、将来的に人事全体のマネジメントや組織開発、制度設計などにステップアップする上でも強い土台になります。
まとめ|今日から採用の負担を軽くする一歩を
採用担当者の「きつい」「つらい」という悩みの多くは、個人の努力不足ではなく、限られた人員・時間・仕組みの中で複雑化した業務構造に起因しています。
しかし、採用プロセスの見直しやツールの導入、そして社内連携の強化によって、その負担は確実に軽減できます。
中でも、採用ページの作成から掲載・運用までを一括で支援してくれるFREE JOBは、限られたリソースでも成果を上げたい企業にとって心強い味方です。
採用は、企業の未来をつくる重要な仕事です。一人で抱え込むのではなく、ツールとサポートを上手に組み合わせながら「ラクに、そして成果の出る採用体制」を築いていきましょう。
\採用支援サービス「FREE JOB」のご相談はこちらから/