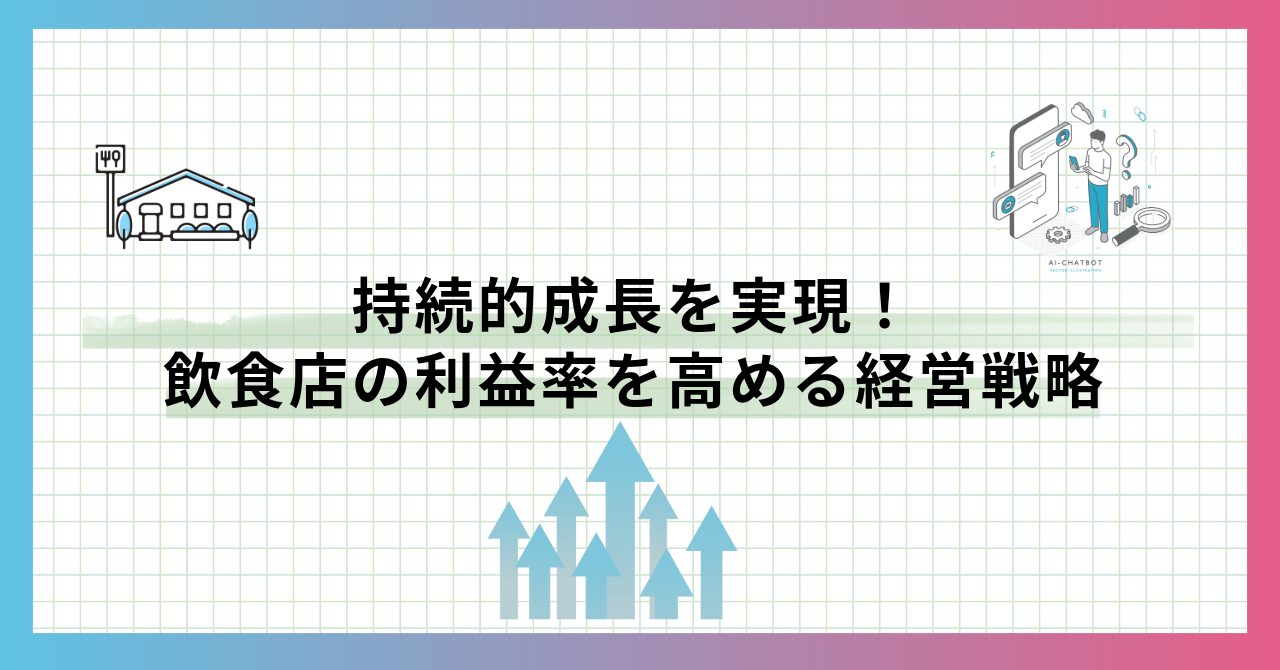飲食店の利益率を高めるための基本知識を徹底解説。利益率の概念、業態別平均値、損益分岐点の算出方法、固定費・変動費の見直し、売上アップ戦略やリピーター施策、デジタル活用まで実践的にまとめました。経営改善のヒントに。
飲食店の利益率向上に必要な基本知識
利益率とは何かを理解する
飲食店経営では、売上よりも重要なのが「利益率」です。利益率は、売上に対してどれだけ利益が残るかを示す指標で、効率よく稼げているかを判断できます。
月商が高くても利益率が低ければお金は残りません。逆に売上が小さくても利益率が高ければ安定した経営が可能です。
だからこそ、経営者は「どれだけ売ったか」ではなく「どれだけ残したか」に目を向けることが重要です。
業態ごとの平均利益率とベンチマーク
自店の利益率が高いのか低いのかを判断するには、業界全体の平均値を知ることが欠かせません。一般的に、飲食店の営業利益率の平均は5〜10%前後といわれています。ただし、これは業態によって大きく異なります。たとえば、回転率の高いラーメン店や立ち食い業態では10%以上を確保できる場合もありますが、客単価が高く仕込みや人件費がかかるレストラン業態では3〜5%程度に留まることも珍しくありません。
また、チェーン店と個人店でも事情は異なります。チェーン店はスケールメリットによる仕入れコストの低減やマニュアル化による効率運営が強みですが、個人店は自由度が高い分、経営者の手腕によって利益率が上下します。つまり、単に平均値を知るだけでなく、「自店のビジネスモデルに合ったベンチマークを設定する」ことが重要なのです。
もし自店の利益率が業界平均を下回っているなら、それは改善余地があるサインです。逆に平均を上回っているなら、その仕組みを分析し、さらなる伸びしろを探る段階にあります。
利益率の正しい計算方法
利益率を正しく把握することは、改善策を立てるうえでの出発点です。基本の計算式は次のとおりです。
利益率(%)= 利益 ÷ 売上 × 100
たとえば月の売上が100万円、経費を差し引いた利益が5万円であれば、利益率は5%となります。これが営業利益率です。単純な式ですが、ここで注意すべきは「どの利益を基準にするか」です。
飲食店の経営分析では、主に以下の3つの段階で利益率を算出します。
- 粗利率(売上総利益率):売上から食材などの原価を引いた後の割合。
- 営業利益率:粗利から人件費や家賃、光熱費などの経費を引いた後の割合。
- 最終利益率:税金や利息なども差し引いた、最終的に残る利益の割合。
店舗運営で重視すべき指標は「営業利益率」です。経営者がコントロールできる領域であり、数値化することで改善ポイントが明確になります。
利益率の把握は店舗の健康診断と同じで、定期的に確認することで赤字を防ぎ、データに基づいた判断ができます。
利益率の見える化こそ、成功する店舗の共通点であり、経営の第一歩です。
飲食店の経費の内訳
固定費について
固定費とは、売上の増減に関わらず毎月一定額かかる費用のことです。飲食店経営において大きな割合を占める項目であり、原則として削減が難しいため、長期的な視点で最適化することが重要です。
主な固定費には以下があります。
- 家賃・共益費
- 水道光熱費(基本料金)
- 通信費(ネット・電話)
- リース料・減価償却費
- 人件費の固定給部分
- 広告費(年間契約型など)
- 保険料・会計ソフト利用料
固定費が高すぎると利益圧迫の原因となります。
物件の選定や契約内容の見直し、設備リースの適正化、シフト管理による固定給と変動給のバランス調整など、中長期でコントロールする戦略が必要です。
変動費について
変動費とは、売上や客数に応じて増減する費用のことです。店舗の運営状況に合わせて比較的調整しやすく、利益率改善の鍵となります。
主な変動費には以下があります。
- 食材原価(フードコスト)
- ドリンク原価
- パート・アルバイトの時給人件費
- 水道光熱費の従量料金
- テイクアウト容器・備品
- ポイント・クーポンなどの販促費
変動費は、日々の管理によって大きく変動します。
食材ロスの管理、仕入れ先の見直し、適切な原価率設定、シフト最適化などによって、利益率を大きく改善することが可能です。
損益分岐点について
利益率を上げるためには、まず「自分の店がどの売上水準で利益を出せるのか」を正確に把握する必要があります。
多くの経営者が“なんとなく黒字”“なんとなく赤字”の感覚で日々を回していますが、その状態では戦略的な改善はできません。
その基準となるのが「損益分岐点」です。
損益分岐点とは
損益分岐点とは、「売上と費用がちょうど釣り合う点」のことを指します。
つまり、赤字にも黒字にもならない、ちょうど利益がゼロになる売上水準です。
この点を下回ると赤字、上回れば黒字になります。
言い換えれば、「損益分岐点をどれだけ超えられるか」が、あなたの店の利益率を決めるのです。
飲食店の場合、費用は大きく「固定費」と「変動費」に分かれます。
この2つを整理し、次の式で損益分岐点を算出します。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
たとえば、月の固定費が100万円、変動費率(原価・人件費などの割合)が70%なら、
損益分岐点売上高は次のようになります。
100万円 ÷(1−0.7)= 約333万円
つまり、月に333万円を売り上げなければ赤字ということです。
この数字を把握していないと、いくら頑張っても「なぜ利益が出ないのか」が見えません。
反対に、損益分岐点を明確にすると、どれだけの売上を目指せばいいかが一目でわかり、経営判断が格段にしやすくなります。
損益分岐点の重要性
損益分岐点の理解は、数字の計算ではなく「経営のリスクを可視化する」ための第一歩です。
固定費や変動費のどこに課題があるかを明確にし、価格設定・販促計画・来店目標など、あらゆる判断をデータに基づいて行えるようになります。
損益分岐点を共有すれば、スタッフ全員が「どこを超えれば利益が出るか」を意識でき、無駄のない店舗運営が実現します。
感覚任せの経営から、数字で利益をコントロールする経営へ変わるための重要な指標です。
利益率を上げるための売り上げアップ方法
コストを最適化することで利益を守る体制が整ったら、次に考えるべきは「売上をいかに伸ばすか」です。
コスト削減だけでは、やがて限界が訪れます。店舗の利益率を本質的に高めるためには、「お客様に選ばれ続ける理由」を明確にし、売上そのものを伸ばす戦略が欠かせません。ここでは、飲食店経営における具体的な売上アップの方法を、実践的な観点から見ていきましょう。
メニューの最適化
メニューは飲食店の利益構造を左右する最重要要素です。ラインナップを闇雲に増やすと原価や人件費が膨らむため、まずは「メニューの棚卸し」が必要です。
POSデータなどで売れ筋・死に筋を分析し、利益率の高い人気商品を中心に再構成しましょう。不要なメニューは改良または削除します。
さらに、食材や工程を共通化することで仕入れと在庫ロスを削減できます。季節限定や数量限定で購買意欲を高めるのも効果的です。
メニューは単なる料理一覧ではなく、戦略的な販売計画です。
価格設定の見直しとテスト
価格設定は利益率を左右する核心要素です。重要なのは「値上げ」ではなく、顧客が価格に見合う価値を感じるかどうかです。
客層や価格感度を踏まえ、ABC分析などで数字を確認しながら、小幅な値上げやセット化で最適価格を探ります。
「980円」のような心理的価格も有効で、価格は数字ではなく戦略です。
プロモーション活動の強化
どれだけ良いメニューでも、知られなければ売上は伸びません。重要なのは、SNSやGoogleビジネスプロフィール、食べログ・Instagramなどで「見つけてもらう仕組み」をつくることです。
Instagramでは料理写真だけでなく、店の雰囲気や体験を伝える投稿が効果的。LINE公式でのクーポン配信やイベント告知も再来店を促します。地域イベント参加や他店とのコラボも認知拡大に有効です。
デジタルと地域の両面からプロモーションを行うことが、売上向上の鍵になります。
顧客単価を上げるための施策
売上を伸ばすには、客数だけでなく「客単価」を上げることが重要です。そのために効果的なのが、アップセル(より高価格へ誘導)とクロスセル(関連メニュー追加)です。
「+200円でドリンクセット」などの提案が大きな利益差を生みます。
セットメニューやペアコースで自然に単価を上げる仕組みづくりも有効です。
メニュー表の配置や写真で高利益商品を目立たせることで選ばれやすくなります。
客単価アップは、無理なく“気持ちよく選んでもらう工夫”が鍵です。
リピーターを増やすための方法
一度来店したお客様に、もう一度足を運んでもらう──この“再来店率”こそが、飲食店の利益を安定させる最大の鍵です。
新規集客には広告費や労力がかかりますが、リピーターの獲得はコストが低く、長期的な利益率向上につながります。
ただし、「リピートしてもらうためのきっかけ」をどうつくるかが課題になります。
そんなときに活用したいのが、CLARiSなどのクーポンサイトです。
CLARiSは200万人超の会員を持つクローズド型クーポンサイトです。新規層へのアプローチと既存客の再来店促進に効果的で、掲載料・送客手数料は永年無料であり、リスクゼロで安定集客ができます。
リピーターを増やすには、料理だけでなく接客や雰囲気など「印象に残る体験」が重要です。
加えて、次回クーポンなど再訪を促す仕組みを整えることで来店を後押しできます。
個別対応でファンを育て、長期的な信頼関係を築くことがリピート戦略の核心です。
テクノロジーの活用で効率化を図る
飲食店経営では、「人手不足」や「業務の属人化」が利益を圧迫する大きな要因となっています。
しかし、デジタル技術の進化によって、これらの課題は着実に解消しつつあります。
テクノロジーを上手に取り入れることで、コスト削減と生産性向上の両立が可能になり、結果として利益率の底上げにつながります。
ここでは、実際に多くの店舗が導入して成果を上げているツールや仕組みを紹介します。
POSシステム導入で売上と在庫を可視化
POSシステムは、飲食店経営の中枢となるツールです。売上や時間帯別・メニュー別のデータをリアルタイムで可視化でき、人員配置や仕入れ量の最適化、原価率改善に役立ちます。
クラウド型POSならスマホやタブレットで手軽に管理でき、経営判断の精度を大きく高められます。
導入コストは下がり、分析機能は高まっています。「スマレジ」のように0円から始められる高機能サービスも登場しています。
スマレジは、43,000店舗以上が利用するクラウドPOSレジで、QR・電子マネー決済対応、リアルタイム売上分析、外部システムとの連携など、中小飲食店でも手軽にデータ経営を実現できる点が特徴です。
「数字に強い経営者」になるための第一歩が、POSシステムの活用なのです。
オンライン注文・予約システムの活用
オンライン注文や予約システムを導入することで、業務効率と顧客満足を同時に高められます。
電話対応に追われる時間が減り、スタッフは調理や接客に集中できるようになります。
また、顧客側にとっても「空席状況をリアルタイムで確認できる」「事前注文で待ち時間を短縮できる」といった利便性が大きな魅力です。
特に、ランチタイムの回転率向上やテイクアウト・デリバリー需要への対応に効果的です。
さらに、予約データを分析することで、リピート率の高い顧客層や人気メニューを把握できます。
その情報をもとに、顧客ごとに最適なキャンペーンを打つなど、次のマーケティング施策へとつなげられる点も見逃せません。
まとめ
飲食店の利益率を上げるために重要なのは、単なるコスト削減や流行施策ではなく、「数字の見える化」と「仕組みづくり」です。原価・人件費・固定費のバランスを把握し、無駄と強みを明確にすることで改善の方向性が見えます。また、コスト管理だけでなく、メニュー設計や価格設定、リピーター育成など、売上向上の戦略も欠かせません。利益率向上とは、短期的なテクニックではなく、継続的に利益を生み出す店を育てるプロセスです。
小さく改善し続けることが、半年後・1年後の安定経営につながります。