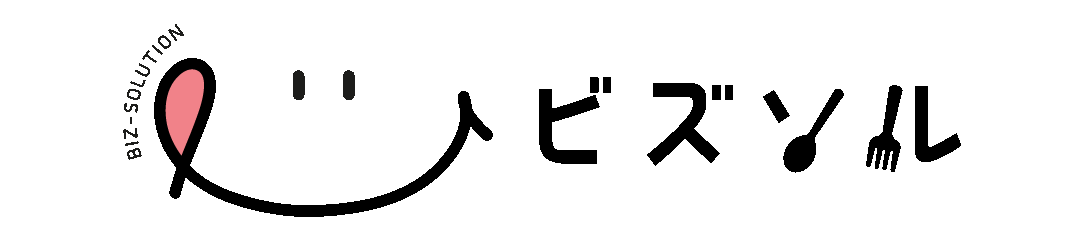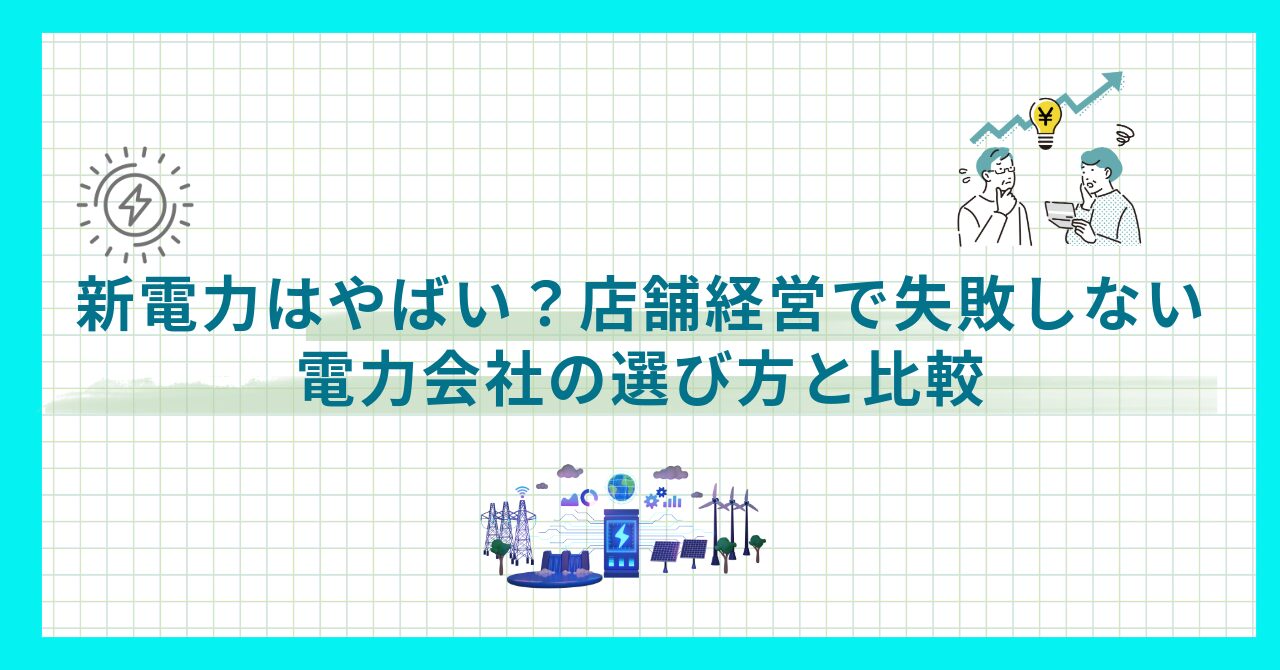電力会社の選択ミスは、店舗経営の安定やコスト管理に大きく影響します。 本記事では「新電力 やばい」と言われる理由やリスクの実態を明らかにし、店舗経営者が失敗しないための電力会社の選び方や比較ポイントをわかりやすく詳しく解説します。
なぜ「新電力はやばい」と言われるのか
電気代削減のために「新電力」に切り替える店舗が増えた一方で、「新電力はやばい」「契約して後悔した」という声も少なくありません。では、なぜこのようなイメージが広まっているのでしょうか。その背景を知ることが、信頼できる電力会社を見極める第一歩です。
新電力市場の現状と時系列推移
新電力(PPS:Power Producer and Supplier)は、2016年の電力自由化によって一般家庭や中小事業者向けに参入が可能になった企業を指します。
当初は「電気代が安くなる」「選べる自由が増える」として注目を集め、2020年には700社以上が乱立するほどのブームになりました。
しかし、2021年以降のエネルギー価格高騰や国際的な燃料調達の不安定化によって、多くの新電力が経営難に陥ります。特に2022年は“新電力ショック”とも呼ばれ、数十社が撤退・倒産。経営基盤の弱い企業ほど影響を受け、契約先の顧客が突如として電力供給を失うケースも相次ぎました。
この急激な市場変化が、現在「新電力=やばい」という印象を生んだ大きな要因です。
新電力会社が撤退・倒産する主な原因
新電力が撤退・倒産に追い込まれる最大の理由は、「仕入れ価格の上昇」と「価格転嫁の難しさ」です。
電力の多くは卸市場(JEPX)で調達されますが、燃料価格が急騰すると仕入れコストが高騰し、販売価格を上げられないまま赤字に陥ります。
加えて、価格競争に巻き込まれた企業は「利益率の薄い契約」を大量に抱え、資金繰りが破綻。十分なリスクヘッジを行わないまま事業を拡大したことも、倒産の連鎖を招きました。
つまり、「安さだけで契約を集めた会社ほど危険」なのです。
撤退・倒産時に起こるリスクと店舗経営者への影響
店舗経営者にとって最も深刻なのは、電力会社の撤退による“供給停止リスク”です。
新電力が撤退した場合、一時的に「最終保障供給(大手電力会社が一時的に供給を引き継ぐ制度)」に切り替わります。しかしこの料金は通常より高額で、場合によっては2倍以上の請求が発生します。
また、再契約先を探す間は電気代の見通しが立たず、コスト管理や経営計画に大きな不確実性を生みます。飲食店や小売業のように光熱費比率の高い業種では、月数万円単位でのコスト上昇が経営を圧迫することも少なくありません。
「安くするつもりが、結果的に高くついた」という事例が後を絶たないのです。
消費者が「やばい」と感じる3つの理由
1つ目は「料金の不透明さ」です。
一見安いように見えて、燃料調整費や再エネ賦課金が別途上乗せされ、最終的に大手電力より高くなるケースがあります。料金体系を理解しづらい契約書も多く、「結局いくらなのか分かりにくい」という不満が目立ちます。
2つ目は「サポート対応の悪さ」。
小規模な会社ではカスタマーサポート体制が整っておらず、トラブル時の対応が遅い・繋がらないといった声も少なくありません。
そして3つ目が「突然の撤退や料金改定」です。
経営不安や市場変動の影響で、契約期間中に急な値上げを行う会社もあり、契約者が不信感を抱く要因となっています。
こうした要素が積み重なり、消費者の間で「新電力はやばい」というイメージが形成されていったのです。
しかし実際には、すべての新電力が危険なわけではなく、信頼性の高い事業者を見極める方法を知ることで、十分にリスクは回避できます。
やばい会社を見抜くための信頼性チェックポイント
「やばい」と言われる新電力が存在する一方で、安定した運営を続ける優良な会社も少なくありません。
違いを生むのは、“企業としての信頼性”を見抜けるかどうかです。
店舗経営者が契約前に最低限チェックしておくべきポイントを整理しておきましょう。
会社の基盤を見る(信用・実績・登録情報)
最初に確認すべきは、その会社がどれほど「基盤のある企業」かという点です。
電力小売事業を行うには、経済産業省への登録が必須ですが、登録済みであってもそれだけで安全とは限りません。
重要なのは、「どのような企業グループに属しているか」「どれくらいの期間、安定して供給を続けているか」という実績面です。
たとえば、大手ガス会社や通信事業者など、他分野に安定収益源を持つ企業は、燃料価格の変動にも比較的強く、撤退リスクが低い傾向にあります。
逆に、事業歴が浅く、資本金が小さい新興企業の場合は、市場変動に対して脆弱です。
また、過去に行政処分や供給停止の報道があった会社は、必ずニュース記事や経産省の公開情報を確認しておきましょう。
「安さ」よりも「信頼できる運営母体かどうか」を最優先に考えることが、リスク回避の第一歩です。
契約内容を見る(解約条件・料金構成・再エネ費)
次に注意すべきは、契約書の中身です。
とくに「基本料金」「従量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」の4項目が、総支払額を左右します。
これらがどのように算出されるか、そして変動のタイミングが明示されているかを必ず確認しましょう。
多くの新電力では、「燃料価格高騰時には料金を改定する場合がある」という条項が設けられています。
ここを見落とすと、想定外の値上げに直面し、経営計画が崩れることもあります。
また、解約時に違約金や最低利用期間が設定されているケースもあるため、複数年契約を結ぶ前には必ず条件を確認しましょう。
「途中で乗り換えたくなった時に、どのくらいのコストで解約できるか」まで把握しておくことが、店舗経営における柔軟性を保つ鍵となります。
サポート体制とリスク対応を見る
電力会社を選ぶ上で見落とされがちなのが、「サポート体制の質」です。
電気は止まることが許されないインフラですから、万一のトラブル対応や請求トラブルへのレスポンスが遅ければ、それだけで業務に支障が出ます。
信頼できる会社は、問い合わせ窓口が明確で、営業時間外の緊急時にも対応できる体制を整えています。
また、契約者ポータルなどで使用量の確認・請求の内訳・契約変更が簡単にできる仕組みがあるかも重要です。
さらに、リスク対応力を測る指標として、「市場連動型契約への対応姿勢」も注目に値します。
市場価格変動の影響をそのまま転嫁する仕組みの会社は、リスクが契約者に直結しやすい一方、固定単価制を維持する企業は自社で一定のリスクヘッジを行っている証拠とも言えます。
このように、サポート面と価格設計の両方から企業の姿勢を読み取ることが大切です。
新電力と大手電力会社の違いと比較
新電力の登場によって、店舗経営者には「電気をどこから買うか」という新しい選択肢が生まれました。
しかし、コスト面での魅力がある一方で、安定性やサポート体制に不安を感じる人も多いのが実情です。
ここでは、大手電力会社と新電力の違いを整理し、どちらが店舗経営に向いているのかを明確にしていきます。
コスト比較:どれくらい安くなる?
まず最も気になるのが「電気代がどれくらい安くなるのか」という点でしょう。
一般的に新電力は、大手電力会社に比べて5〜15%程度安い料金プランを提示することが多いです。
特に使用量が多い飲食店や美容室、24時間営業の店舗では、年間数万円〜十数万円の削減効果が見込めるケースもあります。
ただし、この“安さ”には条件があります。
新電力の多くは、市場価格や燃料費の変動に連動した料金体系を採用しており、原価が高騰すれば電気代も上がります。
つまり、短期的に見れば節約効果は大きいものの、長期的な安定性には注意が必要です。
一方、大手電力会社の料金は安定しています。
急な価格改定が少なく、経営計画の立てやすさという面では優れています。
「月々のコストを確実にコントロールしたい」という経営者には、多少割高でも大手電力を選ぶ価値があるでしょう。
安定性・リスク面の違い
電気は店舗運営の生命線です。
照明、冷暖房、POSレジ、冷蔵庫など、どれか一つ止まっても営業が成り立ちません。
その意味で「安定供給力」は、コスト以上に重要な比較ポイントになります。
大手電力会社は、自社発電設備を持ち、供給網と保守体制が整っています。
災害時やトラブル発生時も迅速な復旧対応が可能で、長年にわたる実績と信頼性があります。
一方、新電力の多くは、電力を自社で発電せず、卸市場(JEPX)から購入して販売しています。
そのため、市場価格の高騰時には調達コストが跳ね上がり、経営を圧迫するリスクが生じます。
さらに、契約者側に影響が及ぶ形で「料金改定」「撤退」「供給停止」が起こることもあるのです。
ただし、すべての新電力が不安定というわけではありません。
大手グループ系や自治体系の新電力は、発電・調達・販売のバランスが取れており、供給リスクが比較的低い傾向にあります。
つまり、「どの新電力か」によってリスクの大きさは大きく変わるのです。
店舗経営者が重視すべき評価ポイント
店舗経営者にとって大切なのは、「単純な安さ」ではなく「安心して長く使えるかどうか」です。
そのためには、以下の3つの観点で電力会社を評価するのがおすすめです。
- 経営基盤の強さ
親会社やグループ企業の規模、事業の多角化状況を確認します。大手系列ほど撤退リスクが低く、長期契約に向いています。 - 料金の透明性
料金体系が明確か、価格改定の条件がわかりやすいかをチェックします。「見積書の段階で最終金額が読めるか」が重要です。 - サポート体制とレスポンス
問い合わせ対応が迅速で、請求・トラブル対応の窓口がしっかりしているかを確認します。飲食店など営業時間が不規則な業種では特に重要です。
これらを踏まえると、コスト重視なら信頼性の高い新電力、安定重視なら大手電力という棲み分けが明確になります。
自店舗の電気使用量やリスク許容度に合わせて、どちらを選ぶかを判断するのが賢明です。
大手電力会社から新電力会社へ乗り換える方法
「新電力に切り替えたいけど、どうすればいいのか分からない」
——そんな声を多くの店舗経営者から聞きます。
しかし、実際の手続きは想像以上にシンプルです。
スマートメーターの普及やオンライン手続きの拡大によって、最短10分で申し込みが完了するケースもあります。
ここでは、店舗経営者が大手電力から新電力へ安全・確実に切り替えるための手順と注意点を、順を追って解説します。
ステップ①:現在の契約内容を確認する
最初に行うべきは、現在契約している電力会社の情報を正確に把握することです。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 契約している電力会社名とプラン名
- 契約電力(kW)または契約容量(A)
- 使用量と料金(直近12か月分が望ましい)
- 契約期間と解約条件(違約金の有無)
これらの情報は「検針票(電気ご使用量のお知らせ)」またはオンラインマイページから確認できます。
このデータが、後の見積もり比較の“基準”になります。
特に注意したいのが解約金の有無です。
一部の大手電力プラン(特に法人契約)では、期間内に解約すると数万円単位の違約金が発生する場合があります。
そのため、契約更新月や自動更新のタイミングも必ず確認しておきましょう。
ステップ②:複数の新電力会社から見積もりを取る
次に、3社以上の新電力会社から見積もりを取得します。
見積もりは、各社の公式サイトまたは法人向け比較サイト(例:エネチェンジBiz、タイナビBIZなど)を利用するとスムーズです。
このとき、以下の条件を同一にして比較することが重要です。
- 契約容量(AまたはkW)
- 使用量(1か月または年間)
- 契約拠点(地域)
見積もり結果を比較する際は、単純な「基本料金+従量料金」だけでなく、
再エネ賦課金や燃料費調整額を含めた総額を確認するようにしましょう。
また、メールや電話対応時の印象もチェックポイントです。
レスポンスの速さや説明の分かりやすさは、その会社のサポート品質を測る指標になります。
ステップ③:契約前に必ず「5項目」を確認する
契約書やプラン説明を受け取ったら、次の5項目を重点的に確認してください。
- 供給実績:どのくらいの期間、どの規模の法人に供給しているか
- 料金体系:固定単価制か、市場連動型か
- 解約条件:途中解約時の違約金・最低利用期間の有無
- サポート体制:問い合わせ対応時間・緊急時連絡先の有無
- 契約書・約款の明確さ:料金改定や燃料調整の条件が明記されているか
特に「市場連動型プラン」を契約する場合は、価格変動のリスク説明を受けたうえで納得できるかを確認することが大切です。
「安い月もあれば高い月もある」構造を理解しておくことで、想定外の請求を防げます。
ステップ④:契約申し込みと切り替え手続き
契約内容に納得したら、新電力会社の申し込みフォームから契約を進めます。
このとき必要な情報は主に以下の通りです。
- 契約者情報(法人名・住所・担当者名)
- 供給地点特定番号(22桁の数字。検針票に記載)
- 現在の電力会社名
- 支払い方法(口座振替またはクレジットカード)
申し込み完了後は、新電力会社が自動的に旧契約の解約手続きを行います。
原則として、利用者が大手電力に直接連絡する必要はありません。
また、スマートメーターが未設置の場合は、地域の電力会社が無料で交換を行います。
立ち合い不要のケースが多く、手続きにかかる負担は最小限です。
ステップ⑤:切り替え完了と請求確認
申し込みから2〜4週間後、切り替えが完了します。
切り替え当日でも停電は発生せず、営業への影響もありません。
供給開始後の最初の請求書で、単価・期間・使用量が契約内容と一致しているかを必ず確認しましょう。
もし不明点があれば、すぐに新電力会社のサポート窓口に問い合わせることでトラブルを防げます。
スムーズな乗り換えのコツ
- 切り替えは閑散期(春・秋)に行うと比較がしやすい
- 使用量データをExcelなどでまとめておくと見積もりが早い
- 店舗移転やリニューアルのタイミングで同時に見直すと効率的
また、切り替え後も半年〜1年おきに契約条件を見直すことで、常に最適な料金とサービスを維持できます。
電力市場は変化が早いため、「契約したら終わり」ではなく、定期的な再チェックがコスト管理の鍵となります。
店舗・法人におすすめできる信頼性の高い電力会社タイプ
「やばい」と言われる新電力が存在する一方で、安定性・信頼性の両面で評価の高い会社も多くあります。
重要なのは、“どのタイプの新電力を選ぶか”という視点です。
ここでは、店舗経営において特に安心して利用できる4つのタイプを紹介します。
大手系列の新電力(例:東京ガス・大阪ガス系)
まずおすすめできるのが、「大手企業のグループ会社が運営する新電力」です。
東京ガス、大阪ガス、中部電力ミライズ、ソフトバンクでんきなど、母体がしっかりした企業は、燃料調達ルートや資金力が豊富で、価格変動への耐性があります。
これらの会社は自社発電所を保有していたり、長期契約で燃料を安定的に確保していたりと、供給の安定性が非常に高いのが特徴です。
また、顧客サポート体制が整っており、法人窓口を設けている会社も多いため、店舗運営における問い合わせ対応もスムーズです。
価格面では最安とは限りませんが、「信頼性」と「サポート力」を重視する店舗経営者にとっては、もっとも安心できる選択肢と言えます。
地域特化型・自治体系の新電力
に注目すべきは、地方自治体や地域企業が設立した「地域新電力」です。
たとえば、熊本電力やみやまスマートエネルギー、京都市のはあとふるエナジーなどが代表的です。
これらの会社は「地産地消エネルギー」を掲げ、地域内で発電・供給を完結させるモデルを採用しています。
地域密着型のため、大手に比べて顧客対応が柔軟で、トラブル時の対応も迅速です。
また、地域経済への還元を重視していることから、売上の一部を地元事業や環境活動に再投資しているケースもあります。
「地域と共に店舗を成長させたい」「地元への信頼を重視したい」という店舗には相性の良い選択肢です。
ただし、規模が小さい会社も多いため、契約前に財務体質や供給実績を確認することが欠かせません。
業務提携・商工会系の新電力
意外と見落とされがちなのが、商工会議所や業界団体と提携して展開される「業務提携型新電力」です。
これらのサービスは、地域の事業者を支援する目的で設立されていることが多く、法人・店舗向けの料金体系やサポートが整っています。
たとえば、商工会経由で加入するプランでは、電気使用量や業種ごとの特性に合わせた割引設定が行われる場合もあり、コストメリットが出やすいのが特徴です。
また、契約後のフォローアップや相談窓口が地域に存在する点も、店舗経営者にとっては安心材料となります。
「初めての電力切り替えで不安」「信頼できる紹介先から契約したい」という場合は、このタイプを検討してみる価値があります。
代表的なサービスの一つが「ハルとくでんき」です。 「ハルとくでんき」は、全国どこでも(沖縄・離島を除く)利用可能で、品質を変えることなく電力をお届けしています。 そのため、これまで通り安心して電気を使い続けることができるのが魅力です。 さらに、事務所・店舗・飲食店など、ご利用状況に合わせた最適なプランを提案してくれるので、自分の業態や規模に合った料金体系を選びやすいのも大きなメリットとなっています。
店舗・企業が失敗しないための電力会社選びの手順
ここまでで、「やばい会社」と「信頼できる会社」を見分けるための視点を整理してきました。
しかし、実際に契約を進める際には、何から始め、どのように比較・確認すればよいのか迷う方も多いはずです。
この章では、店舗経営者が確実に失敗を避けるための実践的な手順を、4つのステップで解説します。
ステップ① 現状の電気料金を把握する
まず最初にすべきことは、今の電気代を正確に把握することです。
比較を始める前に、現在の契約プラン・使用量・基本料金・従量料金単価を確認しておきましょう。
電力会社から届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や、オンライン明細をチェックすれば、月ごとの電気使用量と金額がわかります。
このデータがあれば、見積もりを取った際に「どれくらい安くなるのか」を具体的に比較できます。
また、使用量の季節変動を考慮するために、最低でも過去12ヶ月分の明細を確認しておくのが理想です。
現状を把握していないまま契約すると、「実際には安くなっていなかった」という誤解が生まれやすくなります。
ステップ② 3社以上から見積もりを取る
1社の提案だけで決めるのは危険です。
電力市場は変動が大きく、同じ条件でも会社によって提示額が大きく異なります。
そのため、最低でも3社以上から見積もりを取り、料金体系や条件を比較することが重要です。
比較の際は、単に「単価の安さ」だけを見るのではなく、
- 燃料費調整の上限が設定されているか
- 再エネ賦課金がどのように扱われているか
- 契約期間や違約金の条件
といった「リスク要素」も合わせてチェックしましょう。
見積もりを取る際は、エネチェンジBizなどの法人向け比較サイトを利用すれば、複数社の見積もりを一括で取得できます。
効率よく比較できるため、忙しい店舗経営者にもおすすめです。
ステップ③ 契約前に必ずチェックする5項目
契約前に確認しておくべきポイントは、次の5つです。
- 供給実績:どのくらいの期間、どの規模の法人に供給しているか
- 料金体系:固定単価制か、市場連動型か
- 解約条件:途中解約時の違約金・最低利用期間の有無
- サポート体制:問い合わせ対応時間・緊急時連絡先の有無
- 契約書・約款の明確さ:料金改定や燃料調整の条件が明記されているか
特に注意したいのが、「市場連動型契約」です。
一時的に安く見えても、市場価格の高騰時には想定以上の電気代になるリスクがあります。
契約書に「JEPX価格連動」や「燃料調整単価上限なし」と記載されている場合は、慎重に検討しましょう。
ステップ④ 契約後のトラブル防止策
契約が決まった後も、油断は禁物です。
契約内容が正しく反映されているか、初回請求書で必ず確認してください。
請求金額が想定と違う場合は、すぐに問い合わせを行いましょう。
また、電気使用量のモニタリングを習慣化することで、異常値や料金変動を早期に発見できます。
多くの電力会社では、WEB明細やアプリで日次・月次の使用量を確認できるため、活用すると便利です。
さらに、毎年1回は「契約見直し」を行いましょう。
電力市場や契約条件は常に変化しており、以前より好条件のプランが登場していることもあります。
定期的な見直しを行うことで、無駄なコストを削減しつつ、安定した電力契約を維持できます。
電力会社選びに関するQ&A
新電力の話題を調べると、「やばい」「倒産した」「高くなった」など、不安をあおるような情報が目につきます。
しかし、その多くは背景を正しく理解すれば、過度に心配する必要がないケースがほとんどです。
ここでは、店舗経営者から特によく寄せられる質問をもとに、誤解をひとつずつ整理していきましょう。
Q1. 新電力が倒産したら、電気は止まるの?
いいえ、電気は止まりません。
新電力会社が撤退・倒産しても、契約者の電気供給が途切れることはありません。
その理由は、電力の安定供給を守るために「最終保障供給制度」という仕組みがあるからです。
もし契約していた新電力が撤退した場合、自動的に地域の大手電力会社(東京電力、関西電力など)が一時的に供給を引き継ぎます。
その間に新しい契約先を探せば、停電や営業停止のようなトラブルには発展しません。
ただし、最終保障供給は一時的な救済措置であり、料金が割高に設定されています。
したがって、撤退の報道があった時点で、早めに別の契約先を検討するのが得策です。
Q2. 新電力は結局「安かろう悪かろう」なのでは?
一概にはそう言えません。
確かに、一部の小規模新電力では経営基盤が弱く、十分なサポートを提供できないケースもあります。
しかし現在では、大手ガス会社・通信会社・自治体系など、信頼性の高い新電力が多数登場しています。
例えば「東京ガスの電気」や「大阪ガスの電気」は、大手電力会社と同等の安定性を持ちながら、契約条件によっては料金を抑えることも可能です。
つまり「新電力=やばい」ではなく、「どの会社を選ぶかで差が出る」というのが正しい理解です。
重要なのは、料金の安さだけで判断せず、供給体制・顧客対応・リスク対応力を総合的に比較することです。
Q3. 市場連動型プランは危険なの?
「市場連動型プラン」は、電力市場(JEPX)の取引価格に応じて電気料金が変動する仕組みです。
2022年のように電力卸価格が高騰した際には、請求額が急増する事例が相次ぎ、「危険」という印象を持たれました。
ただし、これは仕組みを理解せずに契約したことが原因であり、プラン自体が悪いわけではありません。
市場連動型は、電力価格が落ち着いている時期にはコストを抑えられるメリットもあります。
飲食店や美容室など、昼間に電力使用が集中する業種では、変動リスクを避けるために「固定単価型プラン」の方が向いていることが多いです。
一方で、営業時間が夜型・深夜型の店舗では、市場価格が安くなる時間帯を活用して、コスト最適化できるケースもあります。
要は、「危険かどうか」ではなく、「自社の使用パターンに合っているか」を基準に判断することが大切です。
Q4. 解約や切り替えは面倒ではない?
実は、電力会社の切り替えは非常に簡単です。
スマートメーターが設置されている場合、工事不要で契約の手続きだけで完結します。
申し込みから供給開始までの期間も、平均で2~3週間程度です。
また、現在の電力会社への解約連絡も、基本的には新しい電力会社が代行してくれます。
ただし、契約期間中に解約すると「違約金」や「解約手数料」が発生するケースもあるため、事前に契約書で確認しておきましょう。
切り替えのタイミングとしておすすめなのは、電気使用量が安定している月(春または秋)です。
繁忙期を避けることで、電力使用量の変動に惑わされず、冷静にコスト比較ができます。
Q5. 「電気料金が安くなる」と営業されたけど、本当に信用していい?
訪問営業や電話勧誘での「安くなります!」というセールストークには注意が必要です。
なかには、料金の一部だけを強調して誤解を招く説明をする業者も存在します。
信頼できる営業担当者を見極めるポイントは次の3つです。
- 提示された見積もりに「再エネ賦課金」「燃料費調整額」が含まれているか
- 契約期間と解約条件が明確に書かれているか
- 料金比較の根拠として、現行契約の検針票を基にしているか
特に、検針票を見ずに「すぐ安くなります」と言う営業は要注意です。
本当に信頼できる会社は、店舗の使用状況を丁寧に確認し、数字で比較したうえで提案してくれます。
誤解を解くことで、リスクは大幅に減らせる
これらのQ&Aを通じて分かるように、「新電力=やばい」という印象の多くは、情報不足や誤解から生まれています。
制度の仕組みを理解し、信頼できる会社を選び、リスクのある契約を避けることで、店舗経営における電力リスクはほぼコントロール可能です。
まとめ
新電力市場は、変化が速く、情報の真偽が混ざり合う世界です。
しかし、正しい知識と信頼できる情報源を持てば、「やばい」と言われるリスクを恐れる必要はありません。
迷ったときは、情報を集めて、比べて、相談する。
その3つを実行するだけで、あなたの店舗にとって最適な電力会社が見えてきます。
電気は、毎日の営業を支える「血流」のような存在です。
だからこそ、安定して流れ続ける環境を整えることこそが、店舗経営者にとって最も賢い選択なのです。